2008年11月17日
さりげないもみじ~曼殊院~
詩仙堂の近くにある門跡寺院の曼殊院。
さりげないところに、日本人の美学を感じます。

曼殊院の大書院前の枯山水庭園。
小書院の赤い毛氈の部分は、屋形船に見立てて、水面に浮かんでいるようです。

中庭には、ひっそりとお地蔵様がたたずんでいました。
ここにも、さりげなくもみじが落ちていました。

曼殊院の周りには、さりげないもみじと鮮やかなもみじが見られました。


さりげないところに、日本人の美学を感じます。
曼殊院の大書院前の枯山水庭園。
小書院の赤い毛氈の部分は、屋形船に見立てて、水面に浮かんでいるようです。
中庭には、ひっそりとお地蔵様がたたずんでいました。
ここにも、さりげなくもみじが落ちていました。
曼殊院の周りには、さりげないもみじと鮮やかなもみじが見られました。
2008年11月17日
散り紅葉~円通寺~
小雨の降る日曜日。
久しぶりに円通寺を訪れました。
もみじは雨に打たれて、散り紅葉になりかけていたのが印象的でした。

小雨が降って、ちょっと気温が上がってきたせいか、比叡山を見ることはできませんでした。
円通寺の庭園は、比叡山を月山にした雄大な借景庭園。
しかし、きょうは、比叡山が見えなかったおかげで、紅葉とコケの緑がとても鮮やかで印象的に見えました。
はじめて訪れた人は、本当に残念だったと思いますが・・・

千両の実ともみじが、赤さの鮮やかさを競いあっていました。

円通寺の門の屋根にももみじが・・・
ここにも、赤と緑のコントラストの美しさが見られました。

久しぶりに円通寺を訪れました。
もみじは雨に打たれて、散り紅葉になりかけていたのが印象的でした。
小雨が降って、ちょっと気温が上がってきたせいか、比叡山を見ることはできませんでした。
円通寺の庭園は、比叡山を月山にした雄大な借景庭園。
しかし、きょうは、比叡山が見えなかったおかげで、紅葉とコケの緑がとても鮮やかで印象的に見えました。
はじめて訪れた人は、本当に残念だったと思いますが・・・
千両の実ともみじが、赤さの鮮やかさを競いあっていました。
円通寺の門の屋根にももみじが・・・
ここにも、赤と緑のコントラストの美しさが見られました。
2008年11月17日
雨のもみじ~山科毘沙門堂~
雨の京都。
色づきだしたもみじも、雨に降られて冷たそう。

山科の毘沙門堂は、朝からの雨で人もまばら。
そんな中でも、紅葉の中に入ると、辺りが明るい感じになるのが不思議です。

お庭の紅葉は、まるで額縁の中の絵のようです。

雨でもみじも散り紅葉になっていましたが、これも趣があっていいかもしれません。

色づきだしたもみじも、雨に降られて冷たそう。
山科の毘沙門堂は、朝からの雨で人もまばら。
そんな中でも、紅葉の中に入ると、辺りが明るい感じになるのが不思議です。
お庭の紅葉は、まるで額縁の中の絵のようです。
雨でもみじも散り紅葉になっていましたが、これも趣があっていいかもしれません。
2008年11月16日
燃える紅葉の中の主役たち~叡山電車貴船口駅~
叡山電車の貴船口駅付近は、紅葉がきれいな駅です。
ライトアップされた駅に、電車が眩しげに入ってきました。

昼間は、真っ赤に色づいた紅葉の中を出発です。

展望列車「きらら」は、紅葉の色と同化していました。

夜の貴船神社での思い出を胸にした人たちが、ライトアップされた貴船口の駅を後にしていきました。

ライトアップされた駅に、電車が眩しげに入ってきました。
昼間は、真っ赤に色づいた紅葉の中を出発です。
展望列車「きらら」は、紅葉の色と同化していました。
夜の貴船神社での思い出を胸にした人たちが、ライトアップされた貴船口の駅を後にしていきました。
2008年11月16日
かがり火に照らされる紅葉~貴船神社~
貴船神社では、日が暮れだすと、かがり火に紅葉が照らされ、赤く染め始めます。

参道までの灯篭には灯がともり、あたりは次第に暗くなっていきました。

お社の近くの灯篭の灯りは、幻想的な世界を演出していました。

水の神様をお祀りする貴船神社も、今宵は、光と炎で演出されていました。


参道までの灯篭には灯がともり、あたりは次第に暗くなっていきました。
お社の近くの灯篭の灯りは、幻想的な世界を演出していました。
水の神様をお祀りする貴船神社も、今宵は、光と炎で演出されていました。
2008年11月16日
東福寺より落ち着けた庭園~泉涌寺~
東福寺から15分ほど東側に歩いてたところにある泉涌寺。
東福寺通天橋の人の多さに比べ、泉涌寺は、本当にゆっくり秋を味わえるお寺です。
特に、御座所庭園は、落ち着いた庭園です。

人が少ないだけに、ゆっくりと紅葉を楽しんでいました。

お昼からは、薄日も差して、色づいた葉っぱが、透明に輝いていました。


そろそろ、散り紅葉も目立ってきました。

紅葉と落葉が混在する季節です。
東福寺通天橋の人の多さに比べ、泉涌寺は、本当にゆっくり秋を味わえるお寺です。
特に、御座所庭園は、落ち着いた庭園です。
人が少ないだけに、ゆっくりと紅葉を楽しんでいました。
お昼からは、薄日も差して、色づいた葉っぱが、透明に輝いていました。
そろそろ、散り紅葉も目立ってきました。
紅葉と落葉が混在する季節です。
2008年11月15日
通天橋の紅葉~東福寺~
午前中うす曇の京都。
東福寺通天橋付近の紅葉は、全山紅葉とまではいきませんが、とてもきれいに色づきだしていました。

通天橋には、紅葉見物の人でいっぱいでした。

赤、黄、オレンジ、色とりどりに紅葉した色彩は、極楽浄土のような華やかさなのでしょうか。


盛んにシャッターを切っている人がいました。

方丈から見た通天橋の紅葉はまだまだでした。

11月下旬ごろに、全山紅葉が楽しめそうです。
東福寺通天橋付近の紅葉は、全山紅葉とまではいきませんが、とてもきれいに色づきだしていました。
通天橋には、紅葉見物の人でいっぱいでした。
赤、黄、オレンジ、色とりどりに紅葉した色彩は、極楽浄土のような華やかさなのでしょうか。
盛んにシャッターを切っている人がいました。
方丈から見た通天橋の紅葉はまだまだでした。
11月下旬ごろに、全山紅葉が楽しめそうです。
2008年11月14日
夕焼けの帰り道~山科にて~
「夕方」から「夜」に導いてくれるこの夕焼けの数分間。
見慣れた貨物も夕焼け空がドラマにしてくれます。

大阪へ向かう特急雷鳥も夕日がまぶしそうでした。

京都方面へ下る湖西線の普通電車も、この時間は、特急と同じ夕日を浴びています。

西大路駅では、夕焼け雲もきれいでした。

反対側を見ると、もうお月様が上がり始めていました。
きょうもいつもといっしょの一日が終わりました。
見慣れた貨物も夕焼け空がドラマにしてくれます。
大阪へ向かう特急雷鳥も夕日がまぶしそうでした。
京都方面へ下る湖西線の普通電車も、この時間は、特急と同じ夕日を浴びています。
西大路駅では、夕焼け雲もきれいでした。
反対側を見ると、もうお月様が上がり始めていました。
きょうもいつもといっしょの一日が終わりました。
2008年11月13日
赤や黄色の色さまざまに~栂尾高山寺の紅葉~
めっきり寒くなった京都。
京都の紅葉の名所は、どんどん色付き始めています。
栂尾の高山寺の紅葉は、まだ全山紅葉には早いようでしたが、赤や黄色の色さまざまに色付いた紅葉が楽しめます。

紅葉には、空の青さが映えます。

参道に根を生やしていた苔むした杉には、もみじの影が映し出されていました。

全山紅葉になったら、さぞかし見事でしょう!


京都の紅葉の名所は、どんどん色付き始めています。
栂尾の高山寺の紅葉は、まだ全山紅葉には早いようでしたが、赤や黄色の色さまざまに色付いた紅葉が楽しめます。
紅葉には、空の青さが映えます。
参道に根を生やしていた苔むした杉には、もみじの影が映し出されていました。
全山紅葉になったら、さぞかし見事でしょう!
2008年11月12日
東寺の満月~東寺五重塔~
東寺の五重の塔は「京都へ着いた!」と感じさせてくれる建物です。
京都駅から一番近くにある世界文化遺産です。
透き通った夜空には満月。

微かな光で、五重の塔が浮き上がっていました。

境内の木々は紅葉しているようです。

南門のお堀には、満月が映って、水面の月は揺れていました。

京都駅から一番近くにある世界文化遺産です。
透き通った夜空には満月。
微かな光で、五重の塔が浮き上がっていました。
境内の木々は紅葉しているようです。
南門のお堀には、満月が映って、水面の月は揺れていました。
2008年11月10日
柿の味覚を満喫~庭の柿が豊作~
今年は、家の庭の柿が豊作です。
富有柿です。
この2年間は不作だったので、久しぶりの豊作です。
きのう、30個ほど採りましたが、まだ、木には4分の3は残っています。
このままだと、カラスさんの餌になってしまいそうです。
特に手入れをしているわけでもないので、野生そのもの。
無農薬!
でも、味は、デリケートな甘さで、グーです。

家の庭には、実のなる木として、梅とカリンと柿があります。
梅とカリンは、私が入院をしたので、結局実を採らないで終わってしまいました。
ですから、きのうは、頑張って収穫。

でも、このままだと、大半はカラスさんのデザートになりそうです。
でも、それも自然でいいのかもしれませんね。
富有柿です。
この2年間は不作だったので、久しぶりの豊作です。
きのう、30個ほど採りましたが、まだ、木には4分の3は残っています。
このままだと、カラスさんの餌になってしまいそうです。
特に手入れをしているわけでもないので、野生そのもの。
無農薬!
でも、味は、デリケートな甘さで、グーです。
家の庭には、実のなる木として、梅とカリンと柿があります。
梅とカリンは、私が入院をしたので、結局実を採らないで終わってしまいました。
ですから、きのうは、頑張って収穫。
でも、このままだと、大半はカラスさんのデザートになりそうです。
でも、それも自然でいいのかもしれませんね。
2008年11月09日
マルチアーチスト光悦が感じた秋~光悦寺~
本阿弥光悦は、徳川家康から鷹峯の地をもらい、この村に芸術村を作りました。
陶芸、漆芸、出版、茶の湯などにも携わったマルチアーティストの光悦。
広い境内には茶室が点在し、光悦の死後、お寺になりました。
それが光悦寺です。

苔むした茶室への門の屋根には、もみじの葉は落ちていました。

茶室のひとつ、太虚庵を囲んでいる垣根が「光悦垣」と呼ばれ、竹で作られた湾曲して垣根で、垣根の高さは入り口が高くて離れるにしたがって低くなっていきます。
多分、茶室から眺めると、狭い庭が、垣根の高低差の目の錯覚で、より広く感じさせる効果を持たせたのではないかと思います。


眼下には、京都市街の街並みが見下ろせます。

このような素晴らしい環境の中で芸術を極めた光悦は80年の人生を過ごしました。


【東山魁夷「京洛四季」の風景を訪ねて】も更新しました。
陶芸、漆芸、出版、茶の湯などにも携わったマルチアーティストの光悦。
広い境内には茶室が点在し、光悦の死後、お寺になりました。
それが光悦寺です。
苔むした茶室への門の屋根には、もみじの葉は落ちていました。
茶室のひとつ、太虚庵を囲んでいる垣根が「光悦垣」と呼ばれ、竹で作られた湾曲して垣根で、垣根の高さは入り口が高くて離れるにしたがって低くなっていきます。
多分、茶室から眺めると、狭い庭が、垣根の高低差の目の錯覚で、より広く感じさせる効果を持たせたのではないかと思います。
眼下には、京都市街の街並みが見下ろせます。
このような素晴らしい環境の中で芸術を極めた光悦は80年の人生を過ごしました。
【東山魁夷「京洛四季」の風景を訪ねて】も更新しました。
2008年11月08日
嵐山もやっと紅葉~渡月橋~
昼前まで雨の残っていた嵐山。
気温は昨日に比べてぐっと下がり、肌寒い天気。
渡月橋付近から、少しだけ上流へ歩くと、急に人影が少なくなります。
保津川の水面に映る嵐山の姿は、まるで鏡に映したような美しさでした。
曇り空だったので、かえって美しく映っていました。

保津川の屋形舟は、ちょっと寒そうでしたが、舟からの眺めは格別だと思いました。

雨のせいか、人出は少なめでしたが、渡月橋付近は、紅葉見物の人で賑わっていました。

渡月橋の向こうに見える嵐山の紅葉はもう少しですが、これが快晴だったら、もう少し鮮やかな色彩が楽しめたことと思います。

近くのもみじは、確かに鮮やかな美しさで色づき始めていました。

これから一気に紅葉も見ごろを迎えそうです。
【東山魁夷「京洛四季」の風景を訪ねて】を更新しました。
気温は昨日に比べてぐっと下がり、肌寒い天気。
渡月橋付近から、少しだけ上流へ歩くと、急に人影が少なくなります。
保津川の水面に映る嵐山の姿は、まるで鏡に映したような美しさでした。
曇り空だったので、かえって美しく映っていました。
保津川の屋形舟は、ちょっと寒そうでしたが、舟からの眺めは格別だと思いました。
雨のせいか、人出は少なめでしたが、渡月橋付近は、紅葉見物の人で賑わっていました。
渡月橋の向こうに見える嵐山の紅葉はもう少しですが、これが快晴だったら、もう少し鮮やかな色彩が楽しめたことと思います。
近くのもみじは、確かに鮮やかな美しさで色づき始めていました。
これから一気に紅葉も見ごろを迎えそうです。
【東山魁夷「京洛四季」の風景を訪ねて】を更新しました。
2008年11月07日
鉄分補給(懐かしい思い出~0系新幹線と蒸気機関車~)
先日の0系新幹線の写真を捜していたら、懐かしい写真が整理されないでいっぱい出てきました。
今、横須賀線が走る新幹線沿いの線路は、一昔前は、品川と鶴見を結ぶ貨物線でした。
略して品鶴線(ひんかくせん)

(多摩川鉄橋付近にて)
川崎には、新鶴見操車場があり、貨物入れ替えの基地でした。
今は、高層ビルが立ち並んでいます。
その頃は、まだまだ蒸気機関車が走り回っていたのですから、この30年近い時の流れは、すごい勢いだったんですね。
そういえば、1970年10月10日に、高島線の電化を記念して、東京駅を出発し、横浜まで蒸気機関車が走りました。
「さよなら蒸気機関車」
東京駅では、0系新幹線といっしょに蒸気機関車を見ることができました。

(1970年10月10日東京駅)
有楽町にあった交通会館ビルの事務所へお願いして、東京駅を出発する勇姿を撮影しました。
でも、その頃は、東京の空は「スモッグ」がひどく、東京駅から出発する姿がかすんでいました。
0系新幹線との同時出発とは、粋なはからいでした。

(1970年10月10日 東京-有楽町)
新鶴見操車場には、EF10もいました。
あの前後にあるデッキが好きでした。

(新鶴見操車場にて)
新鶴見操車場では、蒸気機関車とEF10をいっしょに見ることもできました。

(新鶴見操車場にて)
そして、蒸気機関車の勇姿も、過去の思い出になりました。


(新鶴見操車場付近にて)
時代は、ものすごい速さで動いています。
そんな中でも動かないのが、「思い出」です。
これらの写真を撮った時のことは、きっちり思い出として脳裏に焼き付いています。
そんな大切な「思い出」を思い起こさせてくれたこと。
それが鉄分補給の効果でしょうか。
なお、もっと鉄分補給されたい方は、下記へ。
更新してませんが・・・すいません。
「蒸気機関車っていいな」
今、横須賀線が走る新幹線沿いの線路は、一昔前は、品川と鶴見を結ぶ貨物線でした。
略して品鶴線(ひんかくせん)
(多摩川鉄橋付近にて)
川崎には、新鶴見操車場があり、貨物入れ替えの基地でした。
今は、高層ビルが立ち並んでいます。
その頃は、まだまだ蒸気機関車が走り回っていたのですから、この30年近い時の流れは、すごい勢いだったんですね。
そういえば、1970年10月10日に、高島線の電化を記念して、東京駅を出発し、横浜まで蒸気機関車が走りました。
「さよなら蒸気機関車」
東京駅では、0系新幹線といっしょに蒸気機関車を見ることができました。
(1970年10月10日東京駅)
有楽町にあった交通会館ビルの事務所へお願いして、東京駅を出発する勇姿を撮影しました。
でも、その頃は、東京の空は「スモッグ」がひどく、東京駅から出発する姿がかすんでいました。
0系新幹線との同時出発とは、粋なはからいでした。
(1970年10月10日 東京-有楽町)
新鶴見操車場には、EF10もいました。
あの前後にあるデッキが好きでした。
(新鶴見操車場にて)
新鶴見操車場では、蒸気機関車とEF10をいっしょに見ることもできました。
(新鶴見操車場にて)
そして、蒸気機関車の勇姿も、過去の思い出になりました。
(新鶴見操車場付近にて)
時代は、ものすごい速さで動いています。
そんな中でも動かないのが、「思い出」です。
これらの写真を撮った時のことは、きっちり思い出として脳裏に焼き付いています。
そんな大切な「思い出」を思い起こさせてくれたこと。
それが鉄分補給の効果でしょうか。
なお、もっと鉄分補給されたい方は、下記へ。
更新してませんが・・・すいません。
「蒸気機関車っていいな」
2008年11月06日
「0系」が超特急で走り抜けた時代
あと3週間ほどで、「0系新幹線」の営業運転が終了します。
44年間走り続けたということですから、すごいものです。
関西圏の電車の吊り広告には、「さよなら、夢の超特急」のポスターが掲出されています。

9月に新大阪から姫路まで最後の乗車をした頃は、まだ人も少なかったですが、そろそろ最後を惜しむ鉄道ファンで一杯でしょうね。
「夢の超特急」

超特急で駆け抜けたこの44年間。
開業は、東京オリンピックの年でした。
高度成長のシンボルが、オリンピックであり、「夢の超特急」でした。
でも、高度経済成長の中で駆け抜けたこの44年間で、本当に国民は幸せになったのでしょうか?
幸せ感を味わえたのでしょうか?
何だか人間らしさとか、人間の温かみとかがどんどん薄れていったようで、一抹の寂しさを感じるのは、私だけでしょうか?
丸みを帯びた「0系」の顔を見ていると、人間の温かさみたいものを感じました。
それが、44年の時代だったのかもしれません。

現在、JR西日本の「さよなら夢の超特急」のホームページで映像が流れています。
「さよなら夢の超特急」
(この映像の「0分24秒」で、馬込橋を渡る新幹線が映っています。そこには、昔住んでいた家が映っていました!)
多摩川を渡る0系です。
丹沢の向こうには、富士山が顔を見せていました。
懐かしいワンショットです。

東京駅で出会った0系のお召し列車です。
先頭車両のスカートの白いVサインが、お召し列車の印でした。

「夢の超特急」が走り抜けた時代が、何だか一番素敵だったように思えてきます。
ありがとう夢の超特急!
44年間走り続けたということですから、すごいものです。
関西圏の電車の吊り広告には、「さよなら、夢の超特急」のポスターが掲出されています。
9月に新大阪から姫路まで最後の乗車をした頃は、まだ人も少なかったですが、そろそろ最後を惜しむ鉄道ファンで一杯でしょうね。
「夢の超特急」
超特急で駆け抜けたこの44年間。
開業は、東京オリンピックの年でした。
高度成長のシンボルが、オリンピックであり、「夢の超特急」でした。
でも、高度経済成長の中で駆け抜けたこの44年間で、本当に国民は幸せになったのでしょうか?
幸せ感を味わえたのでしょうか?
何だか人間らしさとか、人間の温かみとかがどんどん薄れていったようで、一抹の寂しさを感じるのは、私だけでしょうか?
丸みを帯びた「0系」の顔を見ていると、人間の温かさみたいものを感じました。
それが、44年の時代だったのかもしれません。
現在、JR西日本の「さよなら夢の超特急」のホームページで映像が流れています。
「さよなら夢の超特急」
(この映像の「0分24秒」で、馬込橋を渡る新幹線が映っています。そこには、昔住んでいた家が映っていました!)
多摩川を渡る0系です。
丹沢の向こうには、富士山が顔を見せていました。
懐かしいワンショットです。
東京駅で出会った0系のお召し列車です。
先頭車両のスカートの白いVサインが、お召し列車の印でした。
「夢の超特急」が走り抜けた時代が、何だか一番素敵だったように思えてきます。
ありがとう夢の超特急!
2008年11月04日
紫式部(ムラサキシキブ)~源氏物語千年紀~
この実は、何という花の実かご存知ですか?

淡紫色の花と紫色の実が特徴のこの花は、この紫の美しさから、女流作家「紫式部」の名前が当てられました。
確かに、鮮やかな紫色の実は光沢があり、太陽に当たると、輝いて見えます。
特に、この実は、たくさんの実が集まっているのが特徴で、実がたくさん重なっていることを、「シキミ」というそうで、「ムラサキシキミ」と呼ばれていたことから、「ムラサキシキブ」となったようです。

2008年は、「源氏物語」が記録の上で確認されるときから、ちょうど一千年になります。
そこで、京都府を中心に、いろんな催しなどが開催されています。
来年の3月まで、まだまだいろんなイベントが開催されていますので、ぜひチェックしてみて下さい。
京都府「源氏物語千年紀事業 -紫のゆかり、ふたたび-」
「源氏物語千年紀委員会」
紫式部の書いた源氏物語。
もののあわれを描いたともいわれる源氏物語。
「もののあわれ」
目に見、耳に聞くものごとに触発されて生ずる、しみじみとした情趣や哀愁。
このような感情は、現代の人々からは失いかけているものかもしれませんが、まだまだ存在する感情だと思います。
そんなことを、この「紫式部」の実を見ながら感じました。

淡紫色の花と紫色の実が特徴のこの花は、この紫の美しさから、女流作家「紫式部」の名前が当てられました。
確かに、鮮やかな紫色の実は光沢があり、太陽に当たると、輝いて見えます。
特に、この実は、たくさんの実が集まっているのが特徴で、実がたくさん重なっていることを、「シキミ」というそうで、「ムラサキシキミ」と呼ばれていたことから、「ムラサキシキブ」となったようです。
2008年は、「源氏物語」が記録の上で確認されるときから、ちょうど一千年になります。
そこで、京都府を中心に、いろんな催しなどが開催されています。
来年の3月まで、まだまだいろんなイベントが開催されていますので、ぜひチェックしてみて下さい。
京都府「源氏物語千年紀事業 -紫のゆかり、ふたたび-」
「源氏物語千年紀委員会」
紫式部の書いた源氏物語。
もののあわれを描いたともいわれる源氏物語。
「もののあわれ」
目に見、耳に聞くものごとに触発されて生ずる、しみじみとした情趣や哀愁。
このような感情は、現代の人々からは失いかけているものかもしれませんが、まだまだ存在する感情だと思います。
そんなことを、この「紫式部」の実を見ながら感じました。
2008年11月02日
新島襄の旧邸~京都・寺町通り~
新島襄は同志社大学の創設者です。
新島襄の住んでいた家は、京都御所の東側に位置する寺町通りにあります。
この家のとなりが、同志社英学校のあった場所で、すなわち、同志社の発祥の地です。
寺町通りに面した旧邸の門構えは、京都の建物そのもの。

しかし、門の中の彼の住まいは、バルコニーのあるしゃれた洋風の外観です。
明治初めのその当時では、非常にめずらしい建物だったことでしょう。

1階の玄関右には、応接間。

この応接間には、奥様の八重さんが演奏していたオルガンが置かれています。
今でも、この足踏みオルガンの演奏会が開かれています。


1階には、食堂と和室のお座敷、そして彼の書斎があります。

そして、トイレは、和と洋をとりいれた板張りの日本でも初めての洋式トイレ。

1階の台所も、当時の京都は土間形式が一般的でしたが、ここは床板が一面に張られ、その上に流しが置かれていました。

正面の階段もしゃれた感じ。

この階段の塗装の剥がれは、きっと新島襄や八重夫人などの上り下りの跡でしょうか。

2階には、寝室。

洋風の窓の向こうは、京都御所。

寝室の横からは、バルコニーに続いています。
そのドアの上は、障子。

2階の和室の居間には、素敵な花が描かれた襖。

1878年(明治11年)9月に竣工したこの新島邸。
今年で130年になります。
明治、大正、昭和、そして平成。
時代も流れ、教育の内容も質も変わっていく中で、あらためてこの空間に身をおいた時、一人の人間の蒔いた一粒の麦が、たった130年でこれほどまでの多くの実を結んだことに、人間の力のすごさ、すばらしさを感じました。

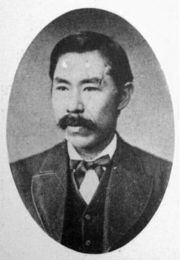
新島襄旧邸のホームページ
新島襄の住んでいた家は、京都御所の東側に位置する寺町通りにあります。
この家のとなりが、同志社英学校のあった場所で、すなわち、同志社の発祥の地です。
寺町通りに面した旧邸の門構えは、京都の建物そのもの。
しかし、門の中の彼の住まいは、バルコニーのあるしゃれた洋風の外観です。
明治初めのその当時では、非常にめずらしい建物だったことでしょう。
1階の玄関右には、応接間。
この応接間には、奥様の八重さんが演奏していたオルガンが置かれています。
今でも、この足踏みオルガンの演奏会が開かれています。
1階には、食堂と和室のお座敷、そして彼の書斎があります。
そして、トイレは、和と洋をとりいれた板張りの日本でも初めての洋式トイレ。
1階の台所も、当時の京都は土間形式が一般的でしたが、ここは床板が一面に張られ、その上に流しが置かれていました。
正面の階段もしゃれた感じ。
この階段の塗装の剥がれは、きっと新島襄や八重夫人などの上り下りの跡でしょうか。
2階には、寝室。
洋風の窓の向こうは、京都御所。
寝室の横からは、バルコニーに続いています。
そのドアの上は、障子。
2階の和室の居間には、素敵な花が描かれた襖。
1878年(明治11年)9月に竣工したこの新島邸。
今年で130年になります。
明治、大正、昭和、そして平成。
時代も流れ、教育の内容も質も変わっていく中で、あらためてこの空間に身をおいた時、一人の人間の蒔いた一粒の麦が、たった130年でこれほどまでの多くの実を結んだことに、人間の力のすごさ、すばらしさを感じました。
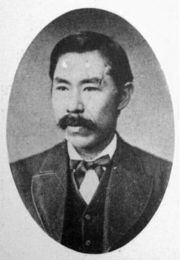
新島襄旧邸のホームページ
2008年11月01日
瀬戸物の故郷にある美しき塀~窯垣(かまがき)~
きょうは、瀬戸物のふるさとの瀬戸市へ。
窯垣(かまがき)の小路を散策しました。
窯垣とは、不用になった窯道具で作った塀や壁。

窯道具とは、窯に入れる時に製品を保護するため使った外側の器のエンゴロ(厘鉢)、それを重ねるための円柱の柱となるツク、そして棚板のエブタなどで、今はもう用を終えたこれらの破棄されるものを、塀や壁を作る際に再利用したものが窯垣です。

人と時間が作った偶然のアートです。

「窯垣の小路資料館」は、明治初期の窯元の家。

ここにある「本業タイル」は、日本のタイルの源流といえるものです。
このすばらしいタイルのお風呂には驚かされます。

そして、このすばらしい男性用便器と足を乗せる台。
洒落てます。

第一の役目を終えたものを、窯垣として再生させ、さらに時を経て、新たな命を与える。
そのアイデアと芸術性のすばらしさ。
それが、「瀬戸物」という言葉が、全国に当たり前のように通じる言葉となった原動力になったのだと思いました。

窯垣(かまがき)の小路を散策しました。
窯垣とは、不用になった窯道具で作った塀や壁。
窯道具とは、窯に入れる時に製品を保護するため使った外側の器のエンゴロ(厘鉢)、それを重ねるための円柱の柱となるツク、そして棚板のエブタなどで、今はもう用を終えたこれらの破棄されるものを、塀や壁を作る際に再利用したものが窯垣です。
人と時間が作った偶然のアートです。
「窯垣の小路資料館」は、明治初期の窯元の家。
ここにある「本業タイル」は、日本のタイルの源流といえるものです。
このすばらしいタイルのお風呂には驚かされます。
そして、このすばらしい男性用便器と足を乗せる台。
洒落てます。
第一の役目を終えたものを、窯垣として再生させ、さらに時を経て、新たな命を与える。
そのアイデアと芸術性のすばらしさ。
それが、「瀬戸物」という言葉が、全国に当たり前のように通じる言葉となった原動力になったのだと思いました。



