2009年07月12日
懐かしい京町屋 (並河靖之七宝記念館)
明治・大正期に活躍した七宝作家の並河靖之氏の旧邸は、「並河靖之七宝記念館」として公開されています。
この家は、御殿造りの母屋と京格子を備えた表屋が連なる珍しい構造。
その表屋は、昔懐かしい京町屋そのものです。
明かり取りの天井窓から、光が差し込んでいます。

おくどさんは、昔のまま。
今にも、京野菜が調理されそうです。

火事除けの阿多古さんのお札。

土間は、土ではなく石が敷かれ、両側にはしっかりとした食器棚が設えてありました。

これも美術品そのものです。

格子の入り口の向こうからは、「わらび~もち♪ かきごおり~♪」 という売り子の声が聞こえてきそうでした。

この家は、御殿造りの母屋と京格子を備えた表屋が連なる珍しい構造。
その表屋は、昔懐かしい京町屋そのものです。
明かり取りの天井窓から、光が差し込んでいます。
おくどさんは、昔のまま。
今にも、京野菜が調理されそうです。
火事除けの阿多古さんのお札。
土間は、土ではなく石が敷かれ、両側にはしっかりとした食器棚が設えてありました。
これも美術品そのものです。
格子の入り口の向こうからは、「わらび~もち♪ かきごおり~♪」 という売り子の声が聞こえてきそうでした。
2009年07月12日
七宝の輝きを生んだ館 (並河靖之七宝記念館)
東山三条近くの細り路地にある「並河靖之七宝記念館」
彼は、明治・大正期に活躍した七宝作家。
彼の旧邸の町屋が、記念館となって、生涯手放さなかった希少な作品が展示されています。
庭園の入り口にあるマンホールは、まるで七宝焼きの美しさ。

ここには立派な庭園があり、家は、まるで池の上に建っていてようです。

庭の見える部屋は、すべてガラス張り。
昔の手作りガラスなので、波を打ったようなゆらぎのある透明感が、独特の雰囲気を醸し出しています。

つくばいも大胆な大きさと形です。

池の水は、琵琶湖疎水を取り込むという贅沢さ。

その贅沢な空間が、数々の素晴らしい作品を生む感性を養ったのでしょう。
黒い糸とんぼが、庭に遊びに来ていました。

※彼の作品の素晴らしさは、ホームページでご覧下さい。
http://www8.plala.or.jp/nayspo/
彼は、明治・大正期に活躍した七宝作家。
彼の旧邸の町屋が、記念館となって、生涯手放さなかった希少な作品が展示されています。
庭園の入り口にあるマンホールは、まるで七宝焼きの美しさ。
ここには立派な庭園があり、家は、まるで池の上に建っていてようです。
庭の見える部屋は、すべてガラス張り。
昔の手作りガラスなので、波を打ったようなゆらぎのある透明感が、独特の雰囲気を醸し出しています。
つくばいも大胆な大きさと形です。
池の水は、琵琶湖疎水を取り込むという贅沢さ。
その贅沢な空間が、数々の素晴らしい作品を生む感性を養ったのでしょう。
黒い糸とんぼが、庭に遊びに来ていました。
※彼の作品の素晴らしさは、ホームページでご覧下さい。
http://www8.plala.or.jp/nayspo/
2009年07月11日
茶道と歌道の風を感じて (大徳寺・高桐院)
大徳寺の塔頭のひとつの高桐院。
ここを建立したのは、有名な細川ガラシャの旦那様細川三斎公。
彼は、茶道の奥義を究め、歌道をたしなみ、文武両道に秀でた人。
ここにある有名な茶席は、彼の法名をとって、「松向軒」の名として残されています。

この茶席からは、立派な松の樹が望めます。

それぞれの部屋は、ちょっとした工夫で落ち着きの空間を演出しています。


書院の床に掲げられた書に「関」文字が・・・
「関」とは、「生死のくぎり」を表しています。

この文字は、高桐院の玄関にも掲げられていました。
彼は、83歳の長寿だったそうです。

ここを建立したのは、有名な細川ガラシャの旦那様細川三斎公。
彼は、茶道の奥義を究め、歌道をたしなみ、文武両道に秀でた人。
ここにある有名な茶席は、彼の法名をとって、「松向軒」の名として残されています。
この茶席からは、立派な松の樹が望めます。
それぞれの部屋は、ちょっとした工夫で落ち着きの空間を演出しています。
書院の床に掲げられた書に「関」文字が・・・
「関」とは、「生死のくぎり」を表しています。
この文字は、高桐院の玄関にも掲げられていました。
彼は、83歳の長寿だったそうです。
2009年07月11日
緑深き空間 (大徳寺・高桐院)
大徳寺の塔頭のひとつの高桐院。
有名な細川ガラシャの旦那様細川三斎公によって建立されました。
彼は、茶道の奥義を究め、歌道をたしなみ、文武両道に秀でた人だったそうです。

このつくばいは、「袈裟形のおいつくばい」といい、あの加藤清正が朝鮮王城の羅生門の礎石を持ち帰って、贈られた物だそうです。
石を被う緑が新鮮です。

この半鐘も、1枚の金属ですが、趣きがあります。
どんな音がするのでしょうか?

庭の緑に、ちょっぴり紅色の樹がアクセントになっていました。

有名な細川ガラシャの旦那様細川三斎公によって建立されました。
彼は、茶道の奥義を究め、歌道をたしなみ、文武両道に秀でた人だったそうです。
このつくばいは、「袈裟形のおいつくばい」といい、あの加藤清正が朝鮮王城の羅生門の礎石を持ち帰って、贈られた物だそうです。
石を被う緑が新鮮です。
この半鐘も、1枚の金属ですが、趣きがあります。
どんな音がするのでしょうか?
庭の緑に、ちょっぴり紅色の樹がアクセントになっていました。
2009年07月11日
とろける京わらび餅 (大徳寺・茶洛)
大徳寺を下がったところにある京わらびもちの「茶洛」
ニッキに抹茶。
とろけるおいしさです。

きょうは、抹茶がすでに売り切れ。

抹茶は、またの機会を楽しみに!

今夜のデザートは、とろけるデザートです。
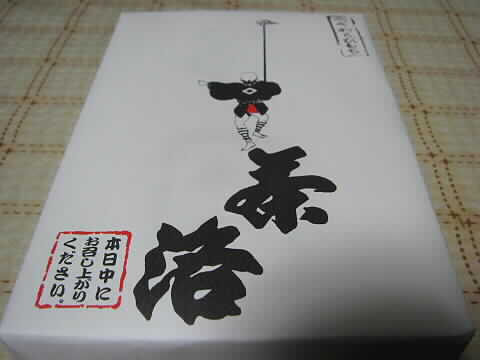
ニッキに抹茶。
とろけるおいしさです。
きょうは、抹茶がすでに売り切れ。
抹茶は、またの機会を楽しみに!
今夜のデザートは、とろけるデザートです。
2009年07月10日
縄を絡めて (祇園祭・月鉾)
祇園祭の鉾建てが始まった京都四条通。
月鉾の鉾建ても、順調でした。
鉾建ては、すべて、荒縄で全体を結わえていきます。
釘を一本も使わないので、ゆさゆさ揺れても倒れません。
これを「縄絡み」といいます。

職人の手で、どんどん縄を絡めていきます。

荒縄が、生き物のようにまとわりついていきます。

その絡めた縄は、芸術品。

今にも飛び立っていきそうな荒縄芸術が、そこにありました。

月鉾の鉾建ても、順調でした。
鉾建ては、すべて、荒縄で全体を結わえていきます。
釘を一本も使わないので、ゆさゆさ揺れても倒れません。
これを「縄絡み」といいます。
職人の手で、どんどん縄を絡めていきます。
荒縄が、生き物のようにまとわりついていきます。
その絡めた縄は、芸術品。
今にも飛び立っていきそうな荒縄芸術が、そこにありました。
2009年07月10日
縄の魔術 (祇園祭・長刀鉾)
祇園祭の山鉾巡行を17日にひかえ、鉾建てが始まりました。
都大路をゆさゆさと巡行する鉾は、どれだけぐらついても大丈夫!
それは、釘を一本も使っていないからです。
すべて、荒縄で全体を結わえていきます。
これを「縄絡み」といいます。
長刀鉾の胴体部分の縄絡み。
蝶が羽を広げているような優雅さです。

この縄絡みも鉾によって違います。

荒縄を人間の力と木槌で、しっかりと絡めていきます。

年期の入った木材が、組み立てられるのを待っていました。

長刀鉾は、毎年、先頭を行きます。

都大路をゆさゆさと巡行する鉾は、どれだけぐらついても大丈夫!
それは、釘を一本も使っていないからです。
すべて、荒縄で全体を結わえていきます。
これを「縄絡み」といいます。
長刀鉾の胴体部分の縄絡み。
蝶が羽を広げているような優雅さです。
この縄絡みも鉾によって違います。
荒縄を人間の力と木槌で、しっかりと絡めていきます。
年期の入った木材が、組み立てられるのを待っていました。
長刀鉾は、毎年、先頭を行きます。
2009年07月08日
京の通りのかぞえ歌 (御池通)
京都の街は、通りが東西南北で碁盤の目状になっています。
ですから、通りの名前も昔から、かぞえ歌になっています。

例えば、南北編では・・・
丸竹夷ニ押御池 姉三六角蛸錦 四綾仏高松万五条
(まるたけえびすにおしおいけ あねさんろっかくたこにしき しあやぶったかまつまんごじょう)
丸太町(まるたまち)
竹屋町(たけやまち)
夷川(えびすがわ)
二条(にじょう)
押小路(おしこうじ)
御池(おいけ)
姉小路(あねこうじ)
三条(さんじょう)
六角(ろっかく)
蛸薬師(たこやくし)
錦小路(にしきこうじ)
四条(しじょう)
綾小路(あやのこうじ)
仏光寺(ぶっこうじ)
高辻(たかつじ)
松原(まつばら)
万寿寺(まんじゅじ)
五条(ごじょう)
これは、京都の道の覚え方です。
丸太町通りから、五条通までです。

東西編では、
寺御幸麩屋富柳堺 高間東車屋町 烏両替室衣
(てらごこうみふやとみやなぎさかい たかあいひがしくるまやちょう からすりょうがえむろころも)
寺町(てらまち)
御幸町(ごこうまち)
麩屋町(ふやちょう)
富小路(とみのこうじ)
柳馬場(やなぎのばんば)
堺町(さかいまち)
高倉(たかくら)
間之町(あいのまち)
東洞院(ひがしのとういん)
車屋町(くるまやちょう)
烏丸(からすま)
両替(りょうがえ)
室町(むろまち)
衣棚(ころもたな)


なかなか粋なかぞえ歌だとおもわはりませんか?
ですから、通りの名前も昔から、かぞえ歌になっています。
例えば、南北編では・・・
丸竹夷ニ押御池 姉三六角蛸錦 四綾仏高松万五条
(まるたけえびすにおしおいけ あねさんろっかくたこにしき しあやぶったかまつまんごじょう)
丸太町(まるたまち)
竹屋町(たけやまち)
夷川(えびすがわ)
二条(にじょう)
押小路(おしこうじ)
御池(おいけ)
姉小路(あねこうじ)
三条(さんじょう)
六角(ろっかく)
蛸薬師(たこやくし)
錦小路(にしきこうじ)
四条(しじょう)
綾小路(あやのこうじ)
仏光寺(ぶっこうじ)
高辻(たかつじ)
松原(まつばら)
万寿寺(まんじゅじ)
五条(ごじょう)
これは、京都の道の覚え方です。
丸太町通りから、五条通までです。
東西編では、
寺御幸麩屋富柳堺 高間東車屋町 烏両替室衣
(てらごこうみふやとみやなぎさかい たかあいひがしくるまやちょう からすりょうがえむろころも)
寺町(てらまち)
御幸町(ごこうまち)
麩屋町(ふやちょう)
富小路(とみのこうじ)
柳馬場(やなぎのばんば)
堺町(さかいまち)
高倉(たかくら)
間之町(あいのまち)
東洞院(ひがしのとういん)
車屋町(くるまやちょう)
烏丸(からすま)
両替(りょうがえ)
室町(むろまち)
衣棚(ころもたな)
なかなか粋なかぞえ歌だとおもわはりませんか?
2009年07月05日
懐かしい風景 (JR南木曽駅付近)
山間に手動式信号機。
蒸気機関車の汽笛が聞こえそうです。

南木曽駅までの旧線。

その旧線に、かつて中央西線で活躍していたD51がいました。

せっかくの記念物なら、もう少し手入れをしてあげたら・・・と思わずにはいられませんでした。

可憐な花だけは、当時と同じく山間に咲き誇っていました。

蒸気機関車の汽笛が聞こえそうです。
南木曽駅までの旧線。
その旧線に、かつて中央西線で活躍していたD51がいました。
せっかくの記念物なら、もう少し手入れをしてあげたら・・・と思わずにはいられませんでした。
可憐な花だけは、当時と同じく山間に咲き誇っていました。
2009年07月05日
2009年07月04日
悟りの窓と迷いの窓 (源光庵)
源光庵の本堂にある二つの窓。
丸と四角。
丸窓は、「悟りの窓」
円で大宇宙、悟りとし、禅と円通の心を表しているそうです。

四角窓は、「迷いの窓」
四角で人間の生涯、迷いとし、生老病死・四苦八苦を表しているそうです。

このふたつの窓が本堂に並んで望むことが出来ます。

私は、四角窓にも落ち着きを感じてしまいましたが、まだ悟りの世界に入っていないのでしょうか・・・
本堂入り口の右側には、丸でも四角でもない窓がありました。
たぶん、自分の心は、このような状態なのかもしれません。
これもまた美し。

紅葉の時は、燃えるような人生を望むことが出来ます。
これもまた楽し。

丸と四角。
丸窓は、「悟りの窓」
円で大宇宙、悟りとし、禅と円通の心を表しているそうです。
四角窓は、「迷いの窓」
四角で人間の生涯、迷いとし、生老病死・四苦八苦を表しているそうです。
このふたつの窓が本堂に並んで望むことが出来ます。
私は、四角窓にも落ち着きを感じてしまいましたが、まだ悟りの世界に入っていないのでしょうか・・・
本堂入り口の右側には、丸でも四角でもない窓がありました。
たぶん、自分の心は、このような状態なのかもしれません。
これもまた美し。
紅葉の時は、燃えるような人生を望むことが出来ます。
これもまた楽し。
2009年07月04日
赤と緑 丸と四角 (源光庵)
源光庵は、京都市北区鷹峯(たかがみね)にある曹洞宗の寺院。
山門の下の土は、赤。
山門の向こうに見える緑と対照的です。

黒い山門の上には、真っ白な丸窓がふたつ。
これも、印象的。

円は大宇宙を表し、また「禅と円通」の心を表しているそうです。
本堂にある丸窓と角窓は有名です。

「赤と緑」「黒と白」「丸と四角」
この対をなす世界に、禅の世界があるのでしょうか。
源光庵の入り口は、緑あざやかな空間でした。

山門の下の土は、赤。
山門の向こうに見える緑と対照的です。
黒い山門の上には、真っ白な丸窓がふたつ。
これも、印象的。
円は大宇宙を表し、また「禅と円通」の心を表しているそうです。
本堂にある丸窓と角窓は有名です。
「赤と緑」「黒と白」「丸と四角」
この対をなす世界に、禅の世界があるのでしょうか。
源光庵の入り口は、緑あざやかな空間でした。



